小学5年生 算数 割合と濃度(2) 【解説付き】無料プリント問題
小学5年生 算数 割合と濃度(2)
小学5年生で学習する「濃度(2)」の問題プリントです。今回の内容は、濃度の基本である「食塩水の全体の重さを求める」計算や、「食塩や水を加えたときの新しい濃度を求める」応用問題、さらに「濃度の異なる食塩水を混ぜたときの濃度を求める」発展的な問題までをバランスよく収録しています。単純な計算にとどまらず、全体量・部分量・割合の関係を整理しながら考える力が必要になるため、割合の理解を深めたいお子さまに最適です。プリントには途中式を書いて考えることを意識できる設問が並んでいるため、ただ答えを出すだけでなく「どうしてそうなるのか」を理解しやすく構成されています。家庭学習や授業の予習復習はもちろん、中学受験の基礎固めとしても活用できる無料プリントです。
▼ダウンロードはこちらから

小学5年生 算数 割合と濃度(2) 解説・回答
上記問題の解説・回答をします。考え方や回答方法などの理解を深めてください。
(1)計算
正答
200g
解説
- 濃度は「食塩 ÷ 全体 ×100」。
- 6 ÷ 全体 ×100 = 3 → 全体 = 6 ÷ 0.03 = 200。
間違えやすいポイント
- 3%を「3」で割ってしまうミス。必ず100で割って「0.03」にしてから計算。

「%」は必ず小数に直してから計算しよう。
(2)計算
正答
300g
解説
12 ÷ 全体 ×100 = 4 → 全体 = 12 ÷ 0.04 = 300。
間違えやすいポイント
- 「12 ÷ 4」で終えてしまうミス。必ず%を小数に。

4%=0.04。これを忘れなければOK。
(3)計算
正答
300g
解説
- 30 ÷ 全体 ×100 = 10 → 全体 = 30 ÷ 0.1 = 300。
間違えやすいポイント
- 10%を「10」と計算して全体を30÷10=3としてしまう。

10%=0.1。ここがカギ。
(4)計算
正答
250g
解説
- 50 ÷ 全体 ×100 = 20 → 全体 = 50 ÷ 0.2 = 250。
間違えやすいポイント
- 分母と分子を逆にして「50÷250」と計算する誤り。

部分 ÷ 全体 ×100=割合、この基本を意識しよう。
(5)計算
正答
300g
解説
- 18 ÷ 全体 ×100 = 6 → 全体 = 18 ÷ 0.06 = 300。
間違えやすいポイント
- 0.06ではなく「6」で割ってしまう。

%を小数に変えるのを忘れない!
(6)計算
正答
44%
解説
- もとの食塩=200×0.3=60g。これに50gを加えると110g。
- 全体=200+50=250g。
- 濃度=110÷250×100=44%。
間違えやすいポイント
- 水も加えたと勘違いしてしまう。今回は食塩だけ増える。

「全体が増えるのか、食塩だけか」を確認しよう。
(7)計算
正答
36%
解説
もとの食塩=200×0.2=40g。+50g=90g。
全体=250g。
濃度=90÷250×100=36%。
間違えやすいポイント
- 加えたのが「水」か「食塩」かを間違えやすい。

問題文をよく読み、「増えたのは何か」をチェックしよう。
(8)計算
正答
15%
解説
食塩の量=150×0.1=15g、150×0.2=30g。合計45g。
全体=300g。
濃度=45÷300×100=15%。
間違えやすいポイント
- 単純に(10%+20%)÷2=15%とやってしまうが、今回は量が同じなのでOK。違う場合は合計を考える。

混ぜ算は「食塩の合計÷全体」。忘れないように。
(9)計算
正答
9.6%
解説
食塩の量=200×0.12=24g、300×0.08=24g。合計48g。
全体=500g。
濃度=48÷500×100=9.6%。
間違えやすいポイント
- 単純に(12%+8%)÷2=10%と計算してしまうミス。量が違うので必ず合計で求める。

混ぜ算は「それぞれの食塩量」を出してから合計!
小学5年生 算数 割合と濃度(2) 保護者向け活用法
濃度の問題は算数の中でも特に苦手とする子が多い単元です。保護者の方は、まず「濃度=食塩の量 ÷ 全体の量 ×100」という基本式を声に出して確認し、計算の意味を理解させてあげると効果的です。また、食塩や水を実際に使って比べたり、ジュースを水で薄める体験を取り入れると、式の意味がぐっと身近になります。間違えやすいのは「%をそのまま計算に使う」ことや「混ぜるときに平均を取ってしまう」ことなので、例題を一緒に確認しながら、必ず「食塩の量の合計 ÷ 全体の合計」で考える習慣をつけましょう。
「基礎はできているけど、応用になると手が止まる…」
「中学受験を考えると、プリントだけで大丈夫かな?」
もしこのような不安を持たれているならば、おすすめしたいのが Z会 です。
下の記事で Z会の特徴・評判・どんな子に向いているか を詳しくまとめました。
まずは無料資料請求で検討するのがおすすめです。
▼こちらも合わせて読みたい!
-723x1024.png)
-100x100.png)

-100x100.png)
-100x100.png)
-100x100.png)

-100x100.png)
-100x100.png)

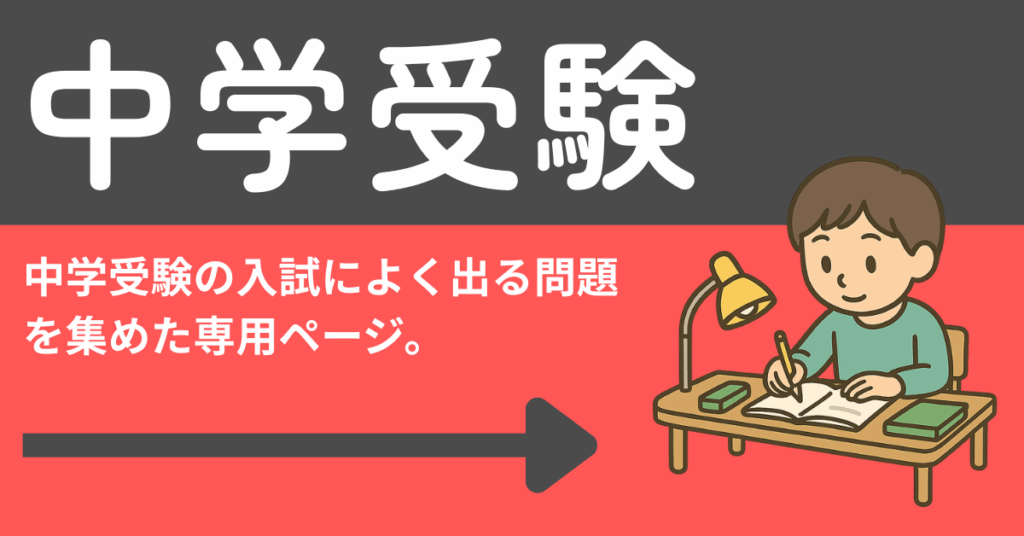
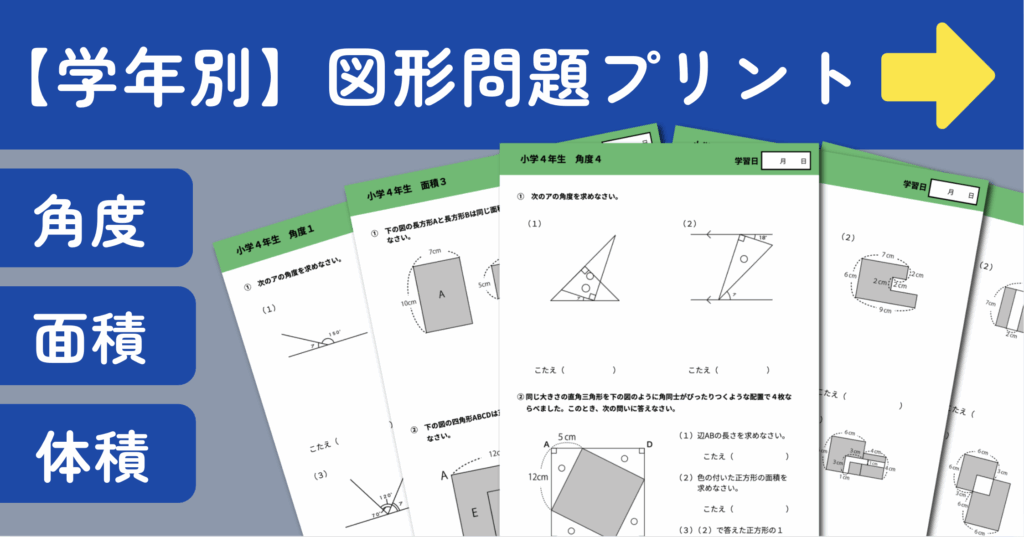

-100x100.png)
-100x100.png)
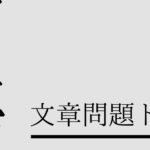


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません