小学4年生 理科 もののあたたまり方 【解説付き】無料プリント問題
小学4年生 理科 もののあたたまり方
小学4年生の理科「もののあたたまり方」を、熱の伝わり方の基本(伝導・対流)から実験の条件のそろえ方まで学べる無料プリントです。金ぞくでは熱がとなりへ広がる(伝導)、木やプラスチックは熱を伝えにくい、不均一にあたためると比較できない—といった大切な視点を、ロウが溶ける順番やスプーンの例、棒の材質比較など身近な題材で理解します。各設問は「正答→解説→間違えやすいポイント→一言ポイント」で構成し、誤りやすい「水は下にあたたかさがたまる」などの思い込みを丁寧に修正。実験では棒の長さ・太さ、火の強さ、位置と時間を同じにするなど、条件制御の考え方も身につきます。家庭学習や授業の予習復習に最適で、無料でダウンロード・印刷可能な実用的プリントです。
ぜひこのプリント問題をご家庭での学習に役立ててください。
でも、正直言って
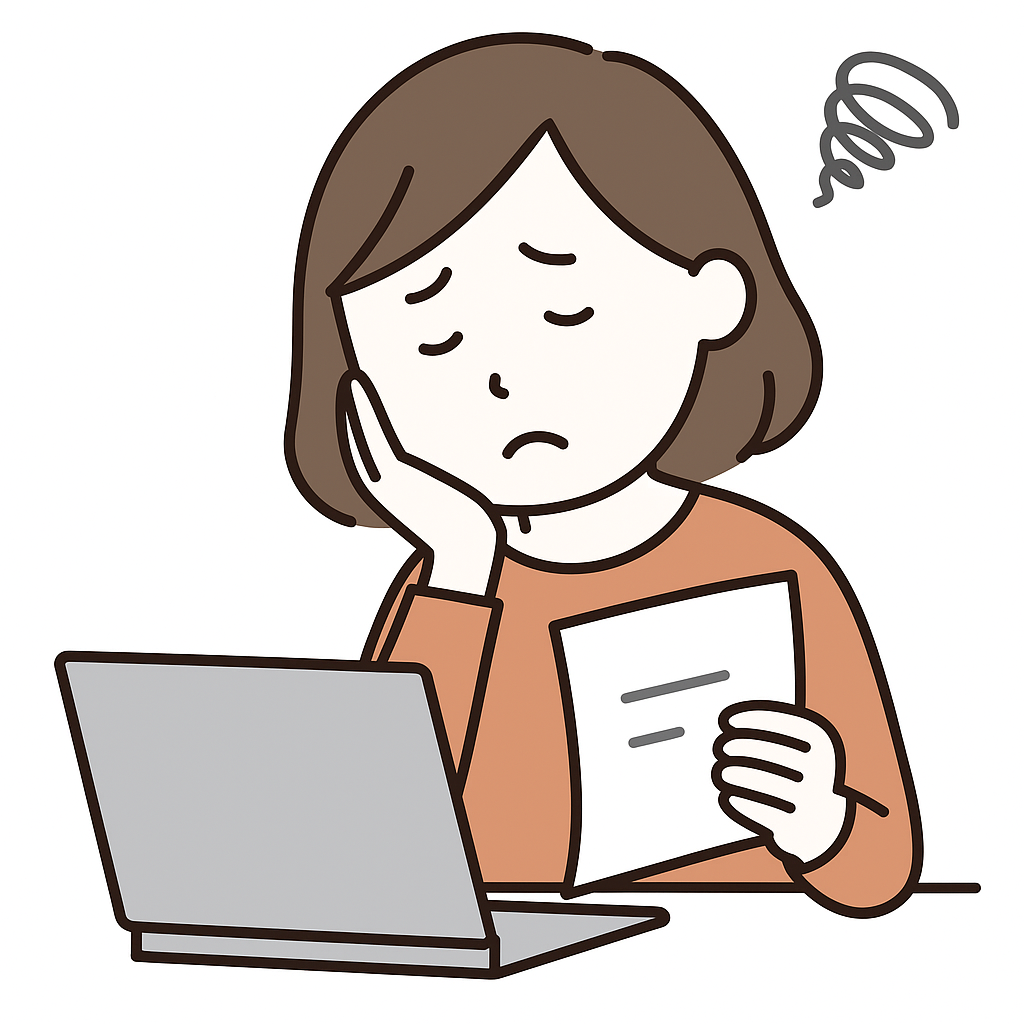
「毎日プリントを探すのめんどくさい…」
「今日は何を勉強させよう…」
って思いますよね。
そんなお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
\でもZ会なら必要な教材が毎月届くから安心!/
1、プリントを探す手間ゼロで保護者の方も時間にゆとりができる!
2、勉強スケジュール管理もおまかせ!
3、良問で学習習慣がつき、成績アップに直結!
これらのお悩みを解決するなら、今すぐチェック!
▼【無料資料請求】でまずは確認してみるといいですよ😃
▼ダウンロードはこちらから
小学4年生 理科 もののあたたまり方 解説・回答
上記問題の解説・回答をします。考え方や回答方法などの理解を深めてください。
① 選択問題
正答
ア/イ/エ
解説
ア 金ぞくは熱が**となりへ伝わる(熱伝導)**ので正しい。
イ 木・プラは**熱が伝わりにくい(不良導体)**ので正しい。
ウ 水はあたためると上へ動く(対流)ため「下にたまりやすい」は誤り。
エ 空気はあたためると上へ動く(対流)ので正しい。
間違いやすいポイント
- 水は下にたまると思いがち(実際は温まった水は軽くなり上へ)。

金ぞく=伝導/水・空気=対流だよ。
② 選択問題
正答
A
解説
熱は加熱端から棒の中を伝導で広がる。最も遠い位置のロウが最後に溶ける。
間違いやすいポイント
- 火から遠い順を取り違える。図の加熱側→遠い側の並びを確認。

遠いほど最後だよ。
③ 記述問題
正答
解答例)金ぞくはあたたかさが伝わりやすいが、木は伝わりにくいため。
解説
金属は熱伝導率が大きいので持ち手まで素早く熱が移る。木は不良導体で伝わりにくい。
間違いやすいポイント
- 「金属は熱いから」「木は冷たいから」など性質(伝導しやすさ)に触れない。

しっかり覚えよう。
④ 選択問題
正答
A/C/D
解説
A 長さ・太さ:違うと伝わり方・時間が変わる。
C 火の強さ:一定でないと入力熱量が変わる。
D あたためる位置・時間:そろえないと比較不可。
色(B)は関係薄く、測る時刻(E)自由は不適切。
間違いやすいポイント
- 見た目(色)を条件に入れてしまう。(見た目は無関係)

形・火・やり方を同じに!
小学4年生 理科 もののあたたまり方 保護者向け活用法
身近な例で実感:金属スプーンと木のスプーンを使って、持ち手の温まり方を比べる。
図で確認:棒の端から矢印で熱が広がる絵を描き、遠いほど遅いことを視覚化。
対流の観察:透明容器に食紅を入れて湯を注ぎ、色の動きが上向きになる様子を見る。
条件をそろえる練習:同じ長さ・太さのストローで息を当てる等、比較実験の基礎を体験。
「基礎はできているけど、応用になると手が止まる…」
「中学受験を考えると、プリントだけで大丈夫かな?」
もしこのような不安を持たれているならば、おすすめしたいのが Z会 です。
下の記事で Z会の特徴・評判・どんな子に向いているか を詳しくまとめました。
まずは無料資料請求で検討するのがおすすめです。
▼こちらも合わせて読みたい!



-100x100.png)

-100x100.png)


-100x100.png)

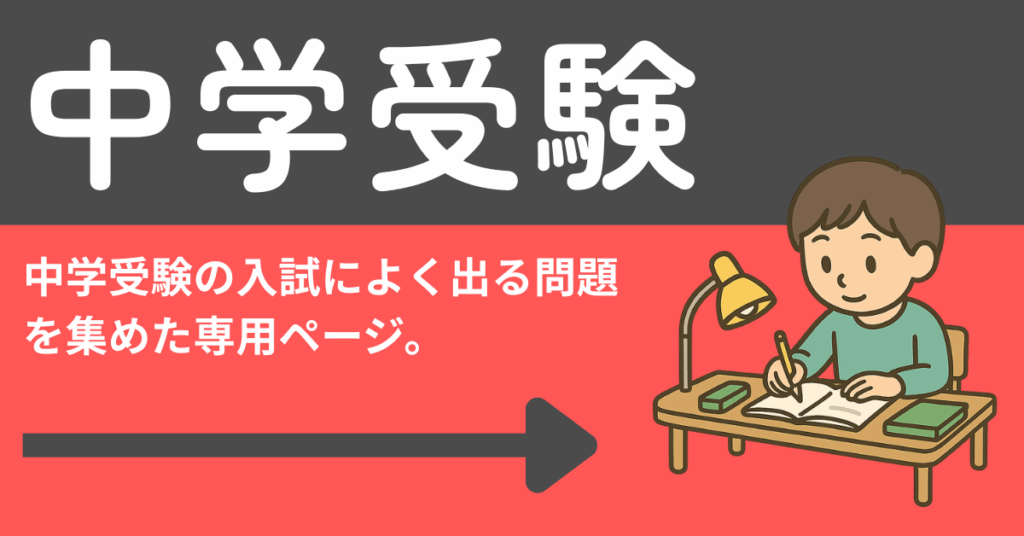
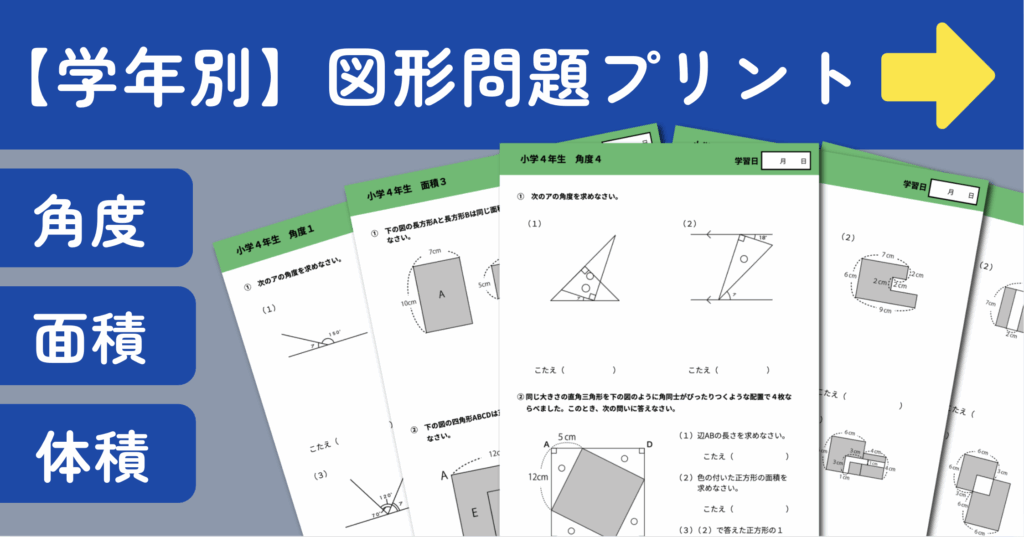


-100x100.png)
-100x100.png)
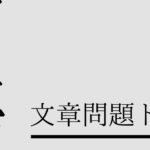


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません