小学3年生 社会 火事をふせぐ 【解説付き】無料プリント問題
小学3年生 社会 火事をふせぐ
小学3年生の社会「火事をふせぐ」の単元では、火事から人々のくらしを守るためのしくみや工夫について学びます。
児童は、消防署の働きや通信司令室の役割、火事を防ぐための設備(消火器・火災報知器など)、地域の防火活動について理解を深めます。また、家庭や学校で自分たちにできる防火の工夫にも目を向け、安全なくらしを守るために大切なことを考える力を育てます。
ぜひこのプリント問題をご家庭での学習に役立ててください。
でも、正直言って
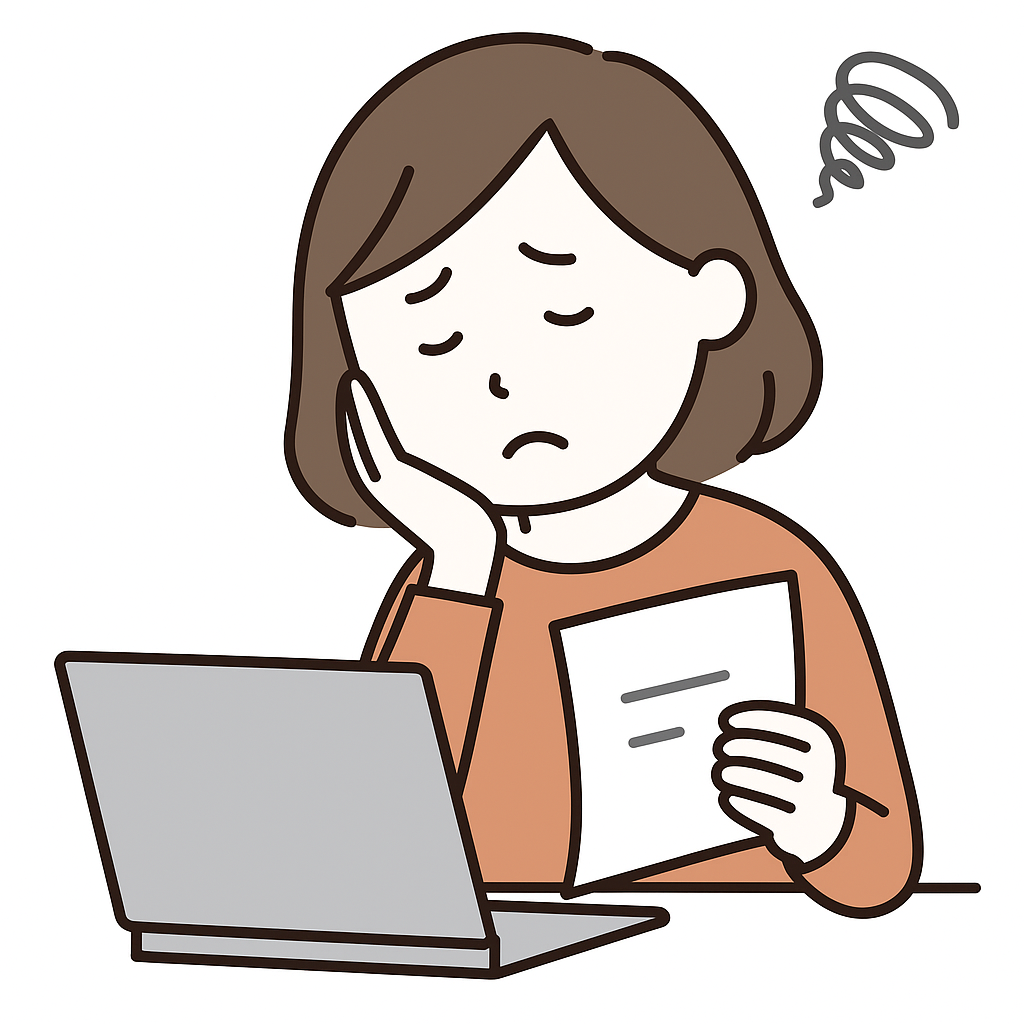
「毎日プリントを探すのめんどくさい…」
「今日は何を勉強させよう…」
って思いますよね。
そんなお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
\でもZ会なら必要な教材が毎月届くから安心!/
1、プリントを探す手間ゼロで保護者の方も時間にゆとりができる!
2、勉強スケジュール管理もおまかせ!
3、良問で学習習慣がつき、成績アップに直結!
これらのお悩みを解決するなら、今すぐチェック!
▼【無料資料請求】でまずは確認してみるといいですよ😃
▼ダウンロードはこちら
小学3年生 社会 火事をふせぐ 解説・回答
上記問題の解説・回答をします。考え方や回答方法などの理解を深めてください。
(1)選択問題
正答
① 火事の場所をたしかめて、近くの消防車に出動の指示を出す
解説
- 消防署の通信司令室は、119番通報を受けたときに火事や事故の場所・状況をすばやく確認し、最寄りの消防署や消防車に出動を指示する重要な場所です。現場で活動する消防隊員に正確な情報を伝える役目もあります。
間違いやすいポイント
- 現場で活動する消防士(②)と混同する
- パトロール(③)と誤解する

「現場で動く人」と「情報を指示する人」は役割が違うことを理解することが大切です。
(2)棒グラフ読み取り問題
正答
① 救急
② 25回
解説
- 棒グラフから、一番多い出動理由は「救急」です。また、火事の回数と救助の回数を足すと25回になります。グラフ問題では、目で見た印象だけで判断せず、数値をしっかり確認することがポイントです。
間違いやすいポイント
- 「火事」が一番多いと勘違いしてしまう
- 足し算を間違える(例:火事15回+救助10回=25回)

棒グラフの読み取りは社会科だけでなく算数の力も必要です。数字を正確に読み取り、計算までできるようにしましょう。
(3) 選択問題
正答
② 火のそばから目をはなさない
③ 使わない電気コードはぬいておく
解説
- 火事を防ぐためには、火や電気を安全に使うことが大切です。火を使っている間は必ずそばにいること、不要な電気コードは抜いて発熱やショートを防ぐことが効果的です。
間違いやすいポイント
- ①ストーブの近くにぬれた服を干す → 危険行為
- ④ライターやマッチで遊ぶ → 火事の原因になる

日常生活の中で火や電気を使う場面を意識して、火事を防ぐ習慣を身につけることが重要です。
小学3年生 社会 火事をふせぐ 保護者向け活用法
この「小学3年生 社会 火事をふせぐ」学習プリントは、消防署の通信司令室の役割や棒グラフの読み取り、防火のための生活習慣について学べる内容です。授業の予習・復習や家庭学習に活用することで、お子さまの防災意識を高められます。
家庭では、プリントの学習後に「もし家で火事が起きたらどう行動するか」を親子で話し合いましょう。また、実際にコンセントの使い方や火の取り扱いルールを確認すると、より実践的な学びになります。
このプリントは、小学3年生の社会科単元「火事をふせぐ」に沿って作成されており、火事予防・防災教育・安全教育の導入にも最適です。お子さまが日常生活の中で危険に気づき、正しい行動がとれるようになるための第一歩となります。
「基礎はできているけど、応用になると手が止まる…」
「中学受験を考えると、プリントだけで大丈夫かな?」
もしこのような不安を持たれているならば、おすすめしたいのが Z会 です。
下の記事で Z会の特徴・評判・どんな子に向いているか を詳しくまとめました。
まずは無料資料請求で検討するのがおすすめです。
▼こちらも合わせて読みたい!




-100x100.png)
-100x100.png)



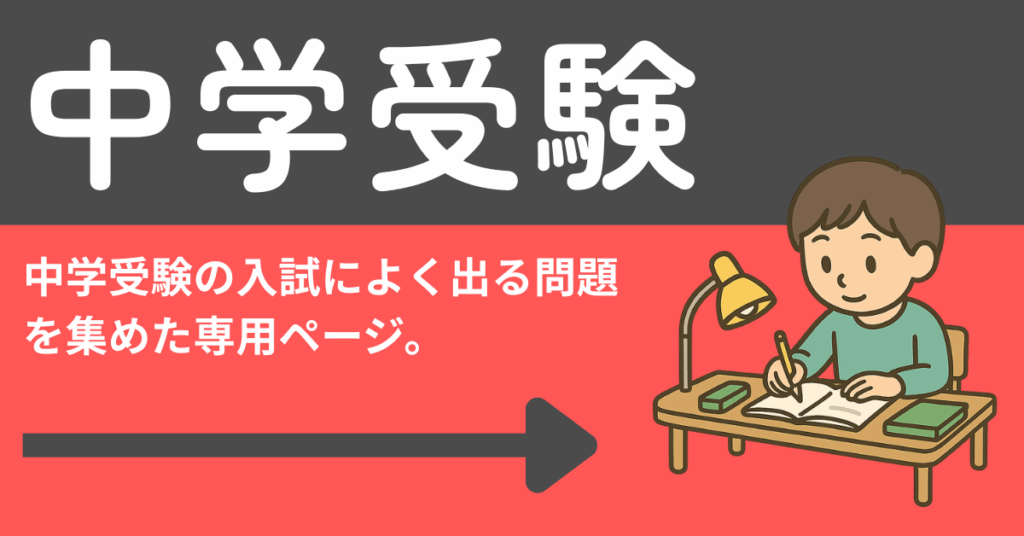
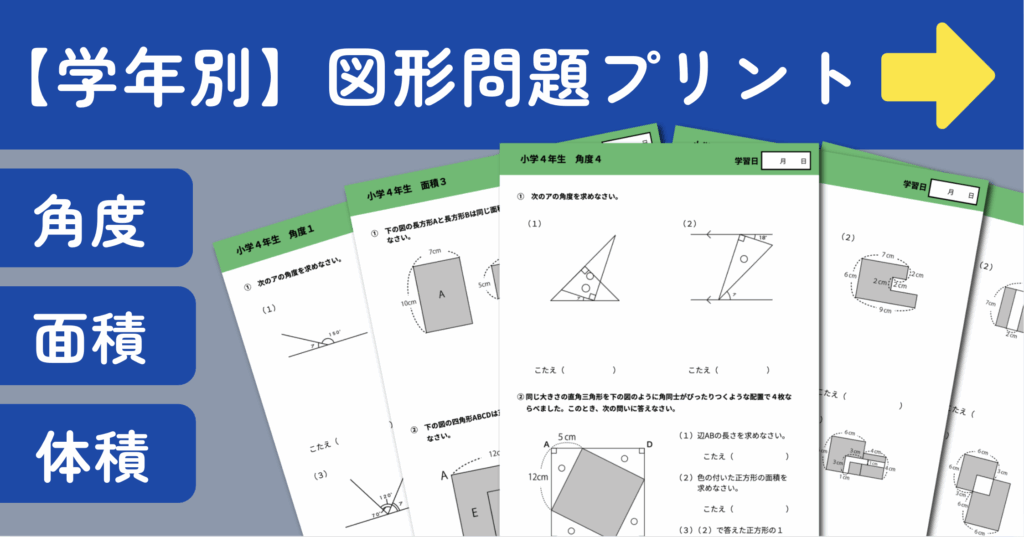


-100x100.png)
-100x100.png)
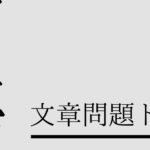


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません