小学3年生 社会 暮らしのうつりかわり 【解説付き】無料プリント問題
小学3年生 社会 暮らしのうつりかわり
小学3年生の社会「くらしのうつりかわり」の単元では、昔と今の人々のくらしのちがいや変化について学びます。家の道具や建物、服装、交通、仕事などの様子を比べることで、生活がどのように便利になってきたのかを理解します。
また、昔のくらしを支えていた人々の工夫や努力にも目を向け、今のくらしとのつながりを考える力を育てます。年表や写真、道具の実物や模型などの資料を活用しながら、時間の流れや変化をとらえる力を身につけることがねらいです。
ぜひこのプリント問題をご家庭での学習に役立ててください。
でも、正直言って
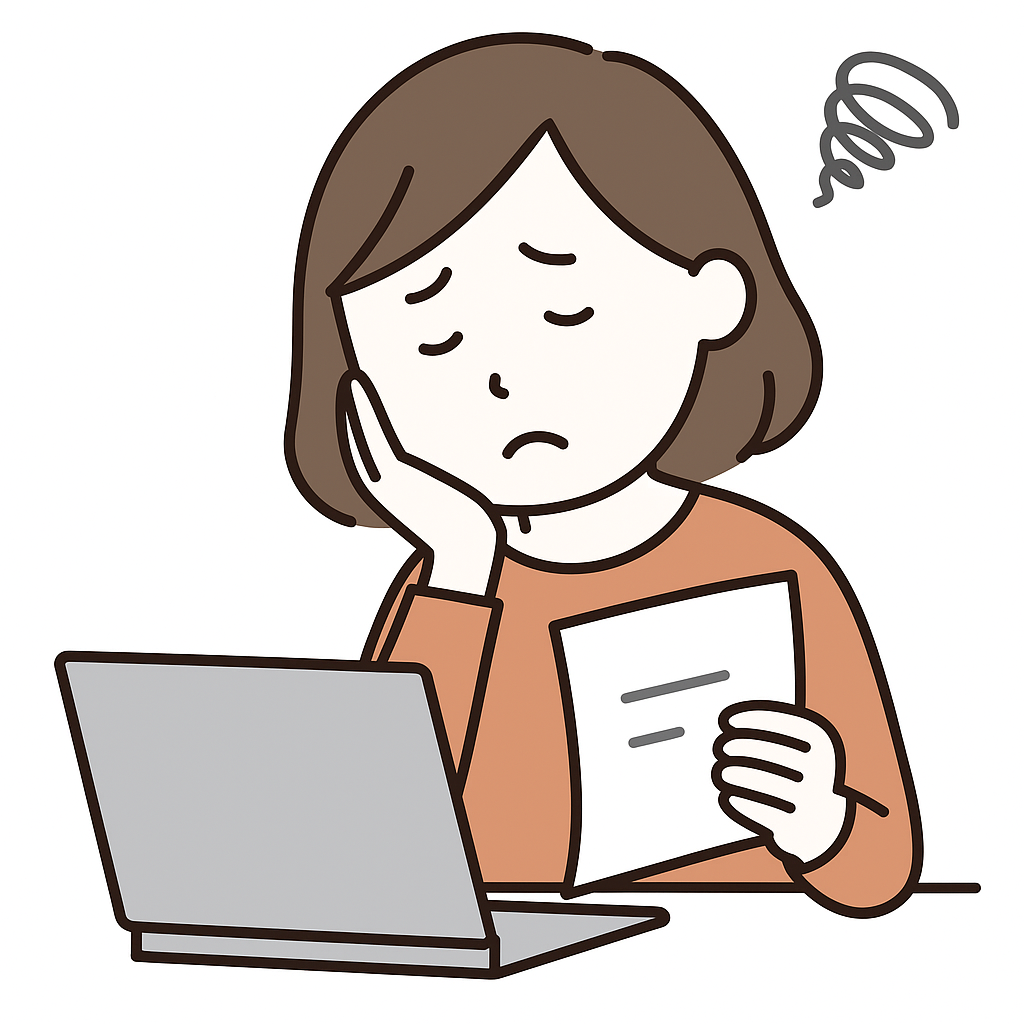
「毎日プリントを探すのめんどくさい…」
「今日は何を勉強させよう…」
って思いますよね。
そんなお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
\でもZ会なら必要な教材が毎月届くから安心!/
1、プリントを探す手間ゼロで保護者の方も時間にゆとりができる!
2、勉強スケジュール管理もおまかせ!
3、良問で学習習慣がつき、成績アップに直結!
これらのお悩みを解決するなら、今すぐチェック!
▼【無料資料請求】でまずは確認してみるといいですよ😃
▼ダウンロードはこちら
小学3年生 社会 暮らしのうつりかわり 解説・回答
上記問題の解説・回答をします。考え方や回答方法などの理解を深めてください。
(1)選択問題
正答
①(B)
②(C)
③(A)
解説
- 昭和のはじめ(1930年代〜1950年代)の洗たくは、洗濯板などを使い、手でこすり洗いをしていました。水くみやしぼりも全て手作業で、非常に時間と力が必要でした。
- 昭和のなかごろ(1960年代〜1980年代)には、洗う槽としぼる槽が分かれた二槽式洗たく機が登場し、水道や電気を使えるようになり、家事が少し楽になりました。
- 平成〜令和(1990年代〜現在)では、ボタンを押すだけで、洗たく・すすぎ・しぼりが全自動でできる洗たく機が主流になり、大きく時間を節約できるようになっています。
間違いやすいポイント
- 二槽式洗たく機(②)と全自動洗たく機(③)を逆に選んでしまう
- 昭和のはじめ(①)の洗濯板を他の時代にあてはめてしまう
- 写真だけで判断して時代背景を考えない

家事の道具は、電気・水道・機械の進歩とともに大きく変化してきました。家で使っている洗たく機と昔の写真を比べてみると、違いがよくわかります。
(2)選択問題
正答
B)今は電気や水道を使って、家事がらくになっている
解説
- 昔は全て手作業で行っていた洗たくも、電気や水道を利用することで、短時間で少ない力で終えられるようになりました。この変化は、家事の効率化だけでなく、家族の生活スタイルにも影響を与えています。
間違いやすいポイント
- 「昔のほうが便利だった」と選んでしまう(実際は今の方が効率的)
- 「今は道具を使わずに手洗い」と誤解する(現在もほぼ全員が道具=洗たく機を使用)

暮らしの道具は「便利さ」「時間短縮」「体の負担軽減」の方向に進化しています。
小学3年生 社会 暮らしのうつりかわり 保護者向け活用法
この「小学3年生 社会 暮らしのうつりかわり」学習プリントは、昭和から平成・令和までの洗たくの道具の変化を通して、生活の進化や家事の効率化について学べる内容です。
家庭学習では、お子さまと一緒に昔の洗濯方法や道具の写真を見比べながら学習することで、理解が深まります。例えば、洗濯板・二槽式洗たく機・全自動洗たく機の画像をインターネットや図鑑で調べると、時代ごとの特徴がより明確にわかります。
また、学習後に「家の中で昔から変わった道具は何があるか?」を親子で探す活動を取り入れると、洗たく以外の家事道具の変化(炊飯器・掃除機・冷蔵庫など)にも興味が広がります。
本プリントは、小学3年生の社会科「暮らしのうつりかわり」単元に沿って作成されているため、授業の予習・復習や自由研究の資料としても最適です。日常生活と学習内容をつなげることで、お子さまの記憶定着が促進され、学習意欲も高まります。
「基礎はできているけど、応用になると手が止まる…」
「中学受験を考えると、プリントだけで大丈夫かな?」
もしこのような不安を持たれているならば、おすすめしたいのが Z会 です。
下の記事で Z会の特徴・評判・どんな子に向いているか を詳しくまとめました。
まずは無料資料請求で検討するのがおすすめです。
▼こちらも合わせて読みたい!





-100x100.png)



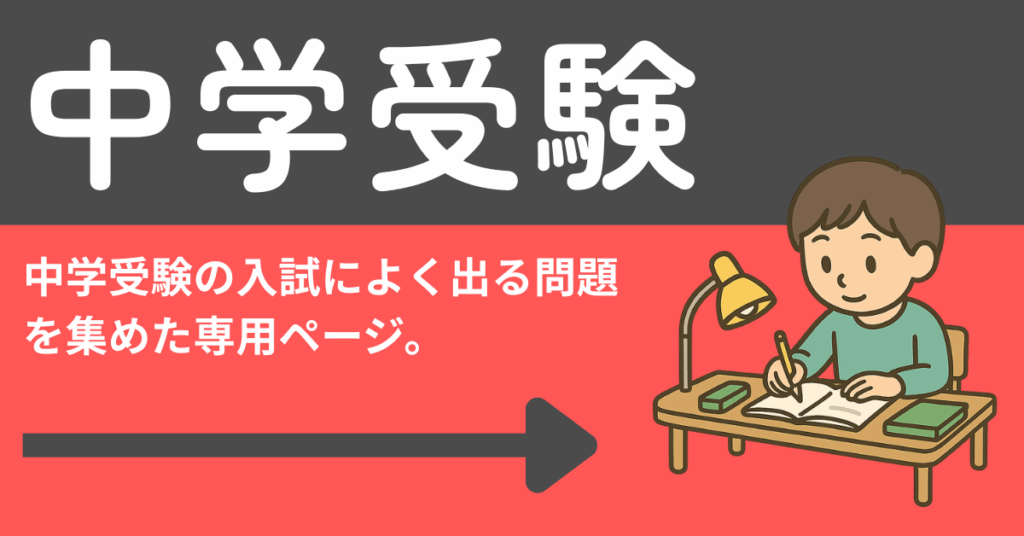
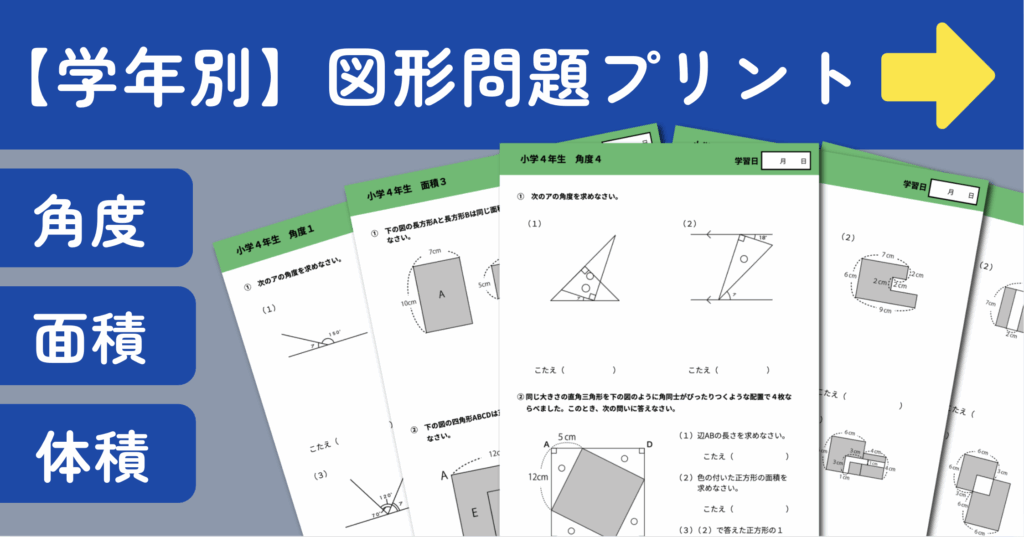


-100x100.png)
-100x100.png)
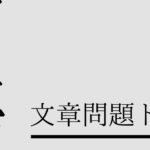


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません