小学3年生 理科 磁石 【解説付き】無料プリント問題
小学3年生 理科 磁石
小学3年生の理科「磁石」の単元では、磁石がもっている不思議な力「磁力」について学びます。まずは磁石が鉄などの特定のものを引きつける性質を観察し、どのようなものに磁石がくっつくか、くっつかないかを調べるところから始まります。さらに、磁石の「N極」と「S極」、同じ極どうしではしりぞけ合い、ちがう極どうしでは引き合うという性質についても実験を通して理解していきます。
また、磁石の形(棒磁石、U字磁石、丸磁石など)や強さのちがい、磁力がはたらく範囲(磁界)なども調べながら、見た目ではわからない磁石の性質を科学的にとらえる力を養います。日常生活の中でも多く使われている磁石のしくみを知ることで、身近な道具への理解も深まります。
この単元では、実際に磁石を動かしたり、くっつけたりしながら、楽しみながら探究心を伸ばせる内容になっています。自分で予想を立てて調べ、結果を比べて考察する力を身につけることも目標のひとつです。
ぜひこのプリント問題をご家庭での学習に役立ててください。
でも、正直言って
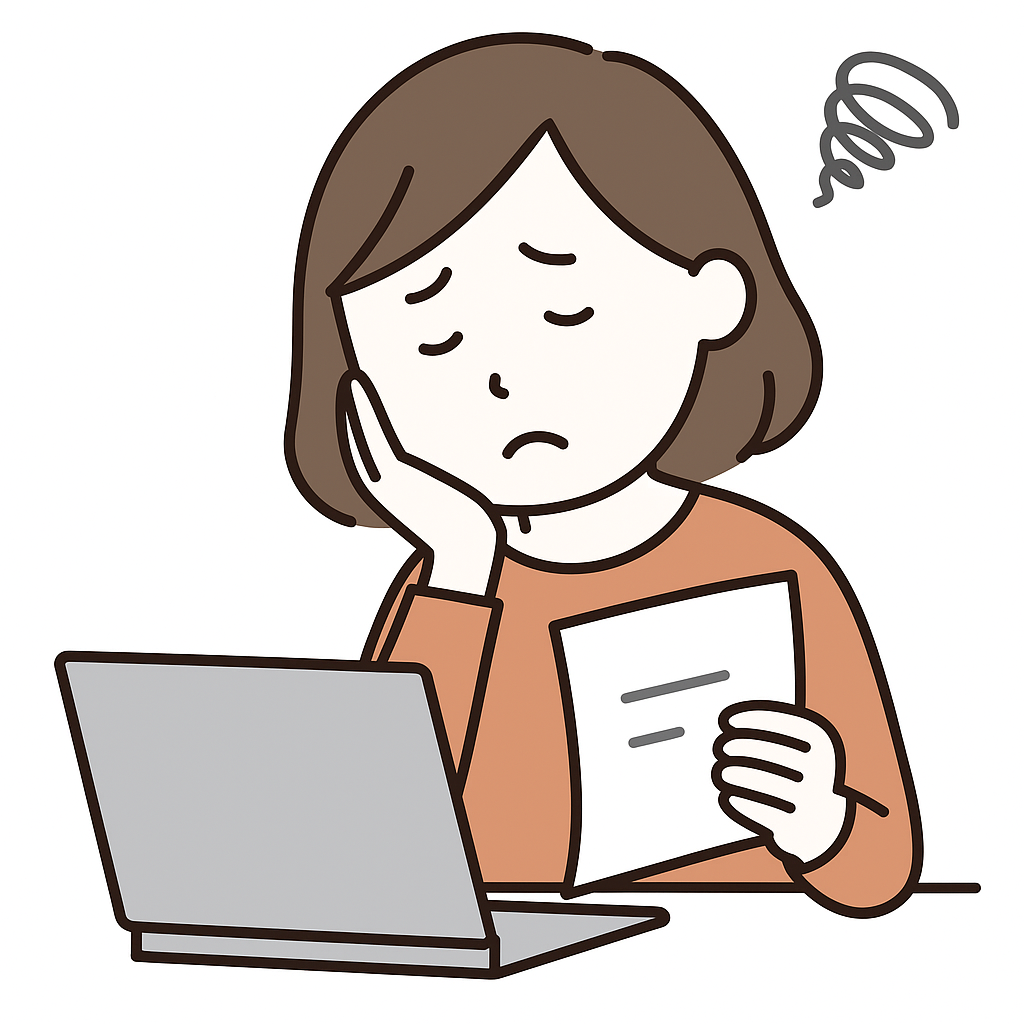
「毎日プリントを探すのめんどくさい…」
「今日は何を勉強させよう…」
って思いますよね。
そんなお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
\でもZ会なら必要な教材が毎月届くから安心!/
1、プリントを探す手間ゼロで保護者の方も時間にゆとりができる!
2、勉強スケジュール管理もおまかせ!
3、良問で学習習慣がつき、成績アップに直結!
これらのお悩みを解決するなら、今すぐチェック!
▼【無料資料請求】でまずは確認してみるといいですよ😃
▼ダウンロードはこちらから
小学3年生 理科 磁石 解説・回答
上記問題の解説・回答をします。考え方や回答方法などの理解を深めてください。
(1) 選択問題
正答
B. U字磁石
解説
グラフを見ると、U字磁石が9個の鉄の玉を引きつけています。他の磁石よりも多くの玉を引きつけたため、磁力が最も強いといえます。
間違いやすいポイント
- 棒磁石Bが7個と多いため、見間違える場合があります。
- グラフの棒の長さだけでなく、実際の数値を確認せずに判断してしまうミスが多いです。

磁石の強さは見た目だけではわからない。実験して数をくらべることで、本当に強い磁石がわかるんだよ。
(2) 選択問題
正答
違う
解説
- 見た目が同じでも、磁石の中の磁石の並び方や材料の違いで磁力は変わります。そのため、同じ形の磁石でも強さが異なることがあります。
間違いやすいポイント
- 「形が同じ=中身も同じ」と思い込んでしまうこと。
- 磁石は外見だけでは性能が判断できない点を見落としがちです。

形が同じでも、中のつくりや材料で磁石の力はちがうことがあるんだ。
(3) 選択問題
正答
B. 距離が遠いと、くっつく数がへる
解説
磁力は距離が遠くなると弱くなる性質があります。7cm離すと、3cmの時よりも少ない数しか引きつけられませんでした。
間違いやすいポイント
- 「遠いとくっつく数がふえる」と思ってしまう誤解。
- 実験結果を数字で比較せず、感覚だけで判断してしまうこと。

磁石の力は、はなれると弱くなって、くっつく数も少なくなるんだ。
(4) 選択問題
正答
C. アルミかんは磁石にくっついた。
解説
- アルミニウムは磁石にくっつかない金属です。鉄やニッケルなど一部の金属だけが磁石にくっつきます。アルミ缶は非鉄金属なので正しくは「くっつかない」が正解です。
間違いやすいポイント
- 「金属=磁石にくっつく」と思い込みやすい。
- アルミや銅など、磁石に反応しない金属があることを知らないケースが多いです。

金ぞくでも、鉄みたいにくっつくものと、アルミみたいにくっつかないものがあるよ。
小学3年生 理科 磁石 保護者向け活用法
この「小学3年生 理科 磁石」の学習プリントは、身近な磁石の性質や使い方を、実験結果や具体的な例を通して理解できるように構成されています。お子さまと一緒に取り組むことで、理科の知識だけでなく、観察力・比較する力・論理的に考える力を育むことができます。
まずはプリントにあるグラフや表を一緒に確認し、「どの磁石が一番強いかな?」「どうして同じ形でも強さが違うの?」と問いかけながら進めると、お子さまが自分の言葉で考えるきっかけになります。また、選択問題だけで終わらせず、「なぜその答えになるのか」を口頭で説明してもらうことで、理解の深まりや表現力の向上につながります。
さらに、家庭にある安全な磁石やスチールクリップ、アルミ缶などを使って、プリントの実験を再現すると効果的です。実際に磁石を近づけたり離したりしながら、くっつく・くっつかないを体験することで、紙上の学びと実体験が結びつき、記憶にも残りやすくなります。
学習後には、磁石が使われている身近な道具(冷蔵庫の扉、バッグの留め具、電化製品のモーターなど)を探してみましょう。生活との関連を見つけることで、「理科は生活に役立つ」という実感を持つことができます。
「基礎はできているけど、応用になると手が止まる…」
「中学受験を考えると、プリントだけで大丈夫かな?」
もしこのような不安を持たれているならば、おすすめしたいのが Z会 です。
下の記事で Z会の特徴・評判・どんな子に向いているか を詳しくまとめました。
まずは無料資料請求で検討するのがおすすめです。
▼こちらも合わせて読みたい!





-100x100.png)
-100x100.png)
-100x100.png)
-100x100.png)


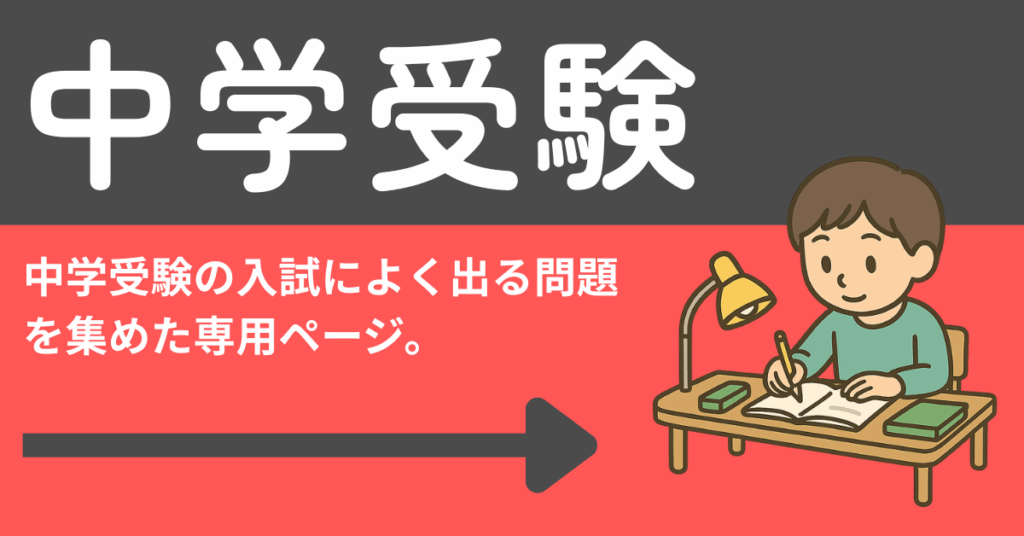
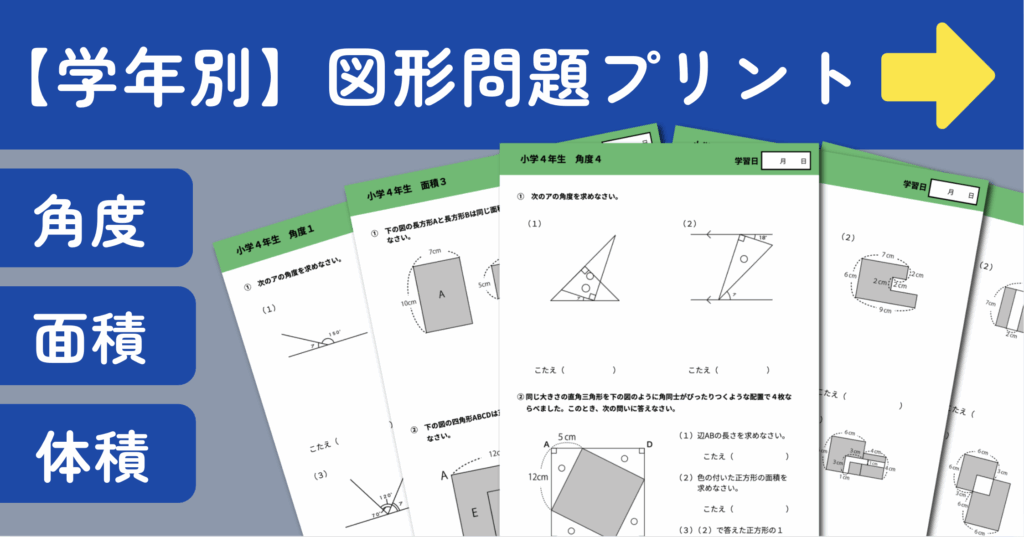


-100x100.png)
-100x100.png)
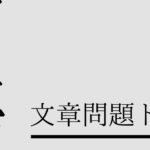


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません