【中学受験の算数】 特殊算 過不足算(基礎2) 解説付き・無料プリント問題
中学受験の算数 特殊算 過不足算(基礎2)
中学受験算数「特殊算・過不足算(基礎2)完全解説|人数変動と余不足から一発で求める連立式・差集めのコツ」。本プリントは「人数を増減させたとき配布数がどう変わるか」「余り・不足をどう式に入れるか」を、配布・買い物・計画変更の定番設定で体系化。式は「総数=単価(または1人当たり)×人数±余不足」に統一し、二式を等置→未知数を解く流れを徹底練習。符号ミスを防ぐチェック法、検算の仕方、入試頻出の“計画→当日変更”型の必勝手順まで網羅し、得点力を底上げします。
ぜひこのプリント問題をご家庭での学習に役立ててください。
でも、正直言って
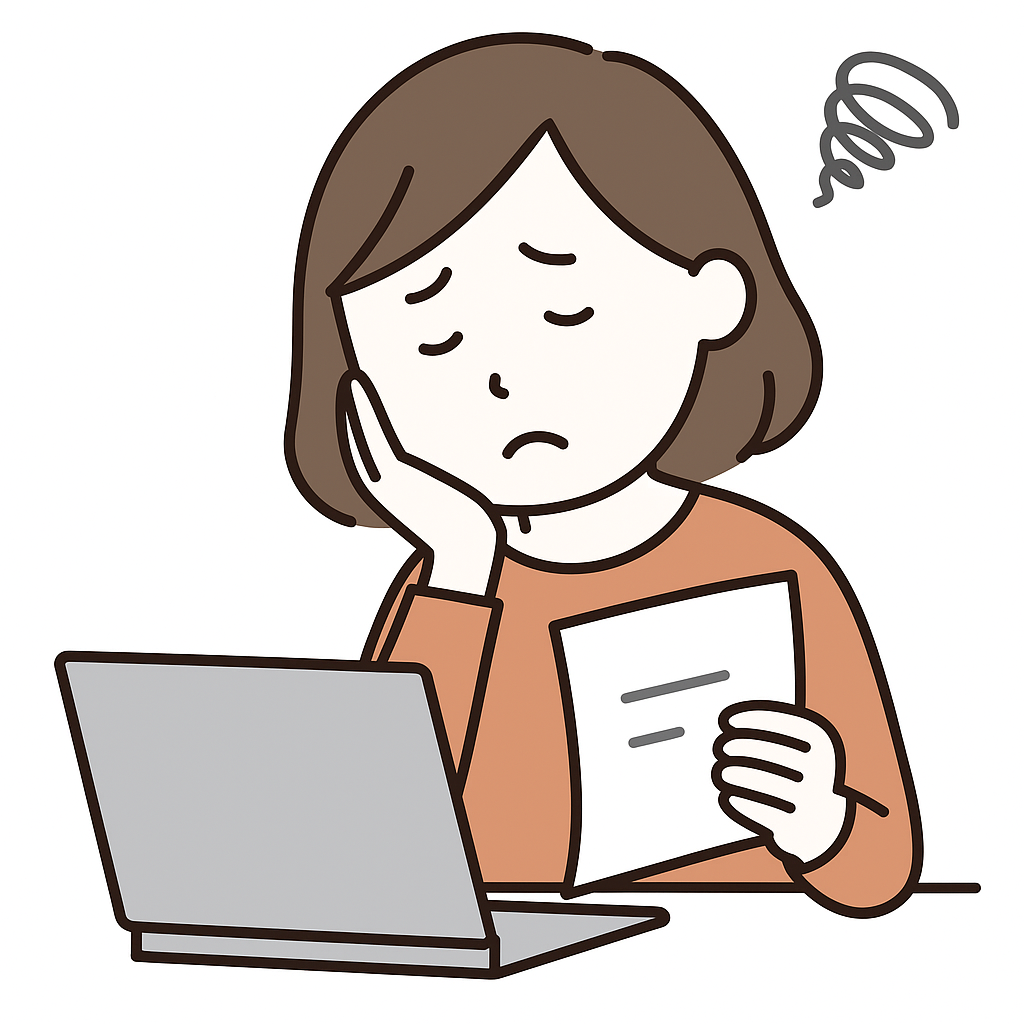
「毎日プリントを探すのめんどくさい…」
「今日は何を勉強させよう…」
って思いますよね。
そんなお悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
\でもZ会なら必要な教材が毎月届くから安心!/
1、プリントを探す手間ゼロで保護者の方も時間にゆとりができる!
2、勉強スケジュール管理もおまかせ!
3、良問で学習習慣がつき、成績アップに直結!
これらのお悩みを解決するなら、今すぐチェック!
▼【無料資料請求】でまずは確認してみるといいですよ😃
▼ダウンロードはこちらから
▼中学受験対策や難しい問題を解きたいならこちらから
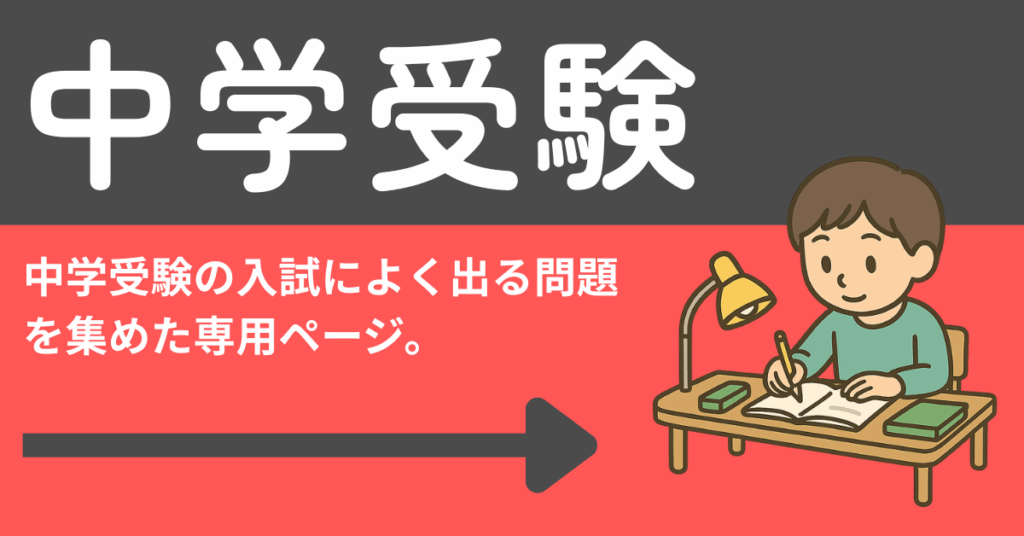
中学受験の算数 特殊算 過不足算(基礎2) 解説・回答
上記問題の解説・回答をします。考え方や回答方法などの理解を深めてください。
(1)計算
正答
29人
解説
「5個ずつの配り方」の人たち全員に、もう2個ずつ足すと「7個ずつの配り方」になります。
このとき足した合計は「2個 ×(5個ずつのときの人数)」です。
いっぽう、7個ずつで考えると、人数は「少ないとき」より「多いとき」が10人多いので、合計は「7個 × 10人 = 70個」ぶん多いはず。
どちらも同じ品物の合計を比べているので、
「2個 ×(5個ずつのときの人数)= 70個」。
だから、5個ずつのときの人数は 70÷2=35人。
5個ずつのときは「本当の人数より6人多い」ので、実際の人数は 35−6=29人。
間違えやすいポイント
7×4=28 と 5×6=30 を引き算して「2人?」などと人と個数をごちゃまぜにする。
人数の差10人に、1人あたりの差2個をかけて「20」としてしまう(何をそろえて比べるかがずれている)。
35人をそのまま答えにしてしまう(それは“5個ずつのとき”の人数。実際はそこから6人ひく)。

「そろえる作戦」がコツ! 5個ずつ→7個ずつに“1人2個”足してそろえて考えると、人数がスッと出せます。
(2)計算
正答
100円
解説
最初はお金が「240円あまる」状態です。
・そこから「さらに3本」買おうとすると、今度は「60円たりない」状態になります。
・ということは、「3本ぶんのねだん」は、あまっていた240円と、たりない60円を合わせた金額になります。
・240円+60円=300円(これが3本ぶん)。
・1本ぶんは 300円÷3=100円。だから1本100円です。
間違えやすいポイント
240と60をひき算してしまう。
・「3本ぶん」をわけ忘れて、300円をそのまま1本の値段だと思ってしまう。
・不足をマイナスと考えて複雑にしてしまう。

「余り+不足=増やした本数ぶんの合計」。あとは本数でわれば1本の値段が出るよ。
(3)計算
正答
500円
解説
「もう1冊ほしい」と思ったとき、今は320円が余っています。
・でも実際に1冊ふやすには、まだ180円足りません。
・ということは、その「1冊ぶんのねだん」は、手元にある320円に、足りない180円をたせば出せます。
・320円+180円=500円。これがノート1冊の値段です。
間違えやすいポイント
余り320円と不足180円をひき算してしまう。
・「不足=マイナス」と考えて符号をつけてしまう。
・1冊の値段ではなく、買える冊数を求めようとしてしまう。

「余り」+「不足」=ちょうど1冊の値段。ここをまっすぐ足し算で出せばOK。
(4)計算
正答
720枚
解説
1、10人が来られなかったので、本当はその人たちに配るはずだった分は9枚×10人=90枚。もし配る数を変えなければ、90枚は余るはずでした。
2、ところが来た人には「1人あたり1枚多く」(9→10枚)配けるので、来た人の人数ぶんだけ余りは減ります。
3、実際の余りは20枚。だから余りは 90→20 に減り、減った分は 90−20=70枚。
4、1人につき1枚ずつ余りが減るので、来た人の人数は 70÷1=70人。
5、来られなかったのは10人だから、はじめの予定の人数は 70+10=80人。
6、カードの合計は 9枚×80人=720枚。
間違えやすいポイント
90−20を反対にしてしまう。
・「減った70枚」をそのまま人数と思ってしまう。
・最後に欠席10人を足し忘れる/合計枚数(9×80)を出し忘れる。

「欠席で余るはずの枚数」と「実際の余り」の差をとり、1人あたり増えた枚数で割る→来た人数。そこに欠席人数を足して予定人数、最後に9枚×予定人数で合計を出そう。
(5)計算
正答
744枚
解説
1、12人が来られなかったので、その人たちに配るはずだった分は
8枚×12人=96枚。もし配る数をそのままにしたら、96枚は余るはずです。
2、でも来た人には「1人あたり1枚多く」9枚ずつ配けるので、来た人の人数分だけ、余りが減ります。
3、実際の余りは15枚でした。余りが96枚 → 15枚 に変わったので、減った余りは 96−15=81枚。
4、余りが81枚減ったのは、「来た人が81人いて、その人たちに1枚ずつ多く配った」からです。だから来た人は81人。
5、来られなかったのは12人なので、予定の人数は 81+12=93人。
6、予定では1人8枚ずつちょうど配れるはずだったので、用意した枚数は8枚×93人=744枚。
間違えやすいポイント
96−15の向きを逆にしてしまう。
・「来た人=81人」から「予定の人数=81+12」を忘れる。
・最後に「人数×8枚」で全体枚数に戻すのを抜かす。

「余りがどれだけ減ったか=来た人の人数」。そこから予定の人数→全体枚数へ戻ろう。
(6)計算
正答
55人
解説
1、12人が来られなかったので、その人たちに配るはずだった分は9個×12人=108個。もし配る数を変えなければ、108個は余るはずでした。
2、ところが来た人には「1人あたり2個多く」(9→11個)配けるので、来た人の人数ぶんだけ余りが減ります。
3、実際の余りは22個。だから余りは 108→22 に減ったことになり、減った分は 108−22=86個。
4、1人につき2個ずつ余りが減るので、来た人の人数は 86÷2=43人。
5、来られなかったのは12人なので、はじめの予定の人数は 43+12=55人。
間違えやすいポイント
108−22を逆にしてしまう。
・「減った86」をそのまま人数と思ってしまう。
・最後に欠席12人を足し忘れる。

「余りがどれだけ減ったか ÷(1人あたり増えた数)=来た人数」→ 最後に欠席を足して予定人数!
中学受験の算数 特殊算 過不足算(基礎2) 保護者向け活用法
過不足算は「もし人や本数が増減したら、合計はどう動く?」を言葉で追う力がカギです。家では実物や図で状況を再現し、「最初の計画」「当日の変化」「余り/不足」を声に出して整理させましょう。学習手順は①総数の式を2本つくる(余りは+、不足は−)②等式で結ぶ③未知数を求め④元の式で検算、の4ステップ。つまずきはたいてい符号と読み取りなので、式の右端に“+余り/−不足”と書くクセ付けが有効です。1日1題でも、“自分で式にできた”達成感を積み重ねると理解が一気に進みます。
「基礎はできているけど、応用になると手が止まる…」
「中学受験を考えると、プリントだけで大丈夫かな?」
もしこのような不安を持たれているならば、おすすめしたいのが Z会 です。
下の記事で Z会の特徴・評判・どんな子に向いているか を詳しくまとめました。
まずは無料資料請求で検討するのがおすすめです。
▼こちらも合わせて読みたい!
-724x1024.png)


-100x100.png)
-100x100.png)
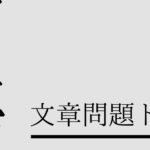
-100x100.png)


-100x100.png)

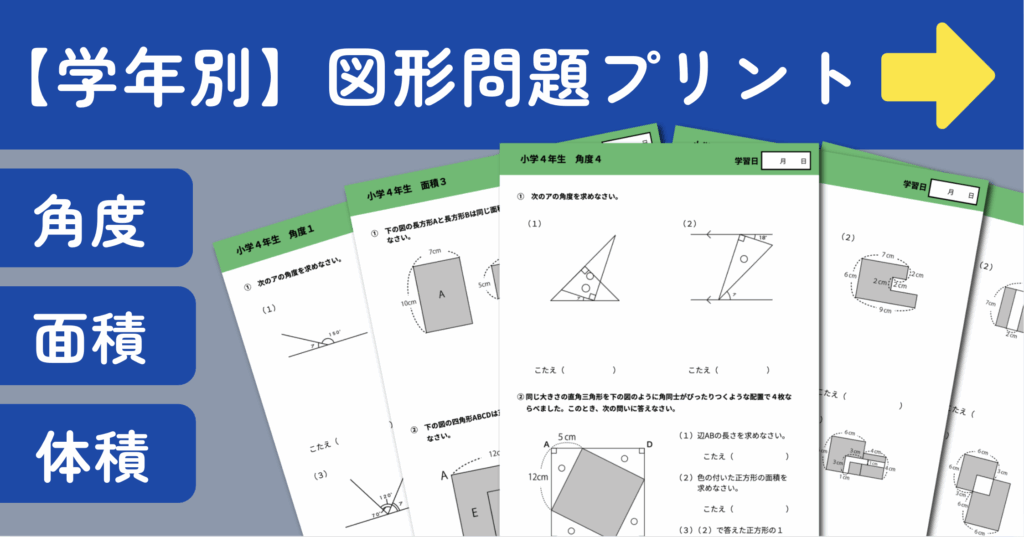


-100x100.png)
-100x100.png)


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません